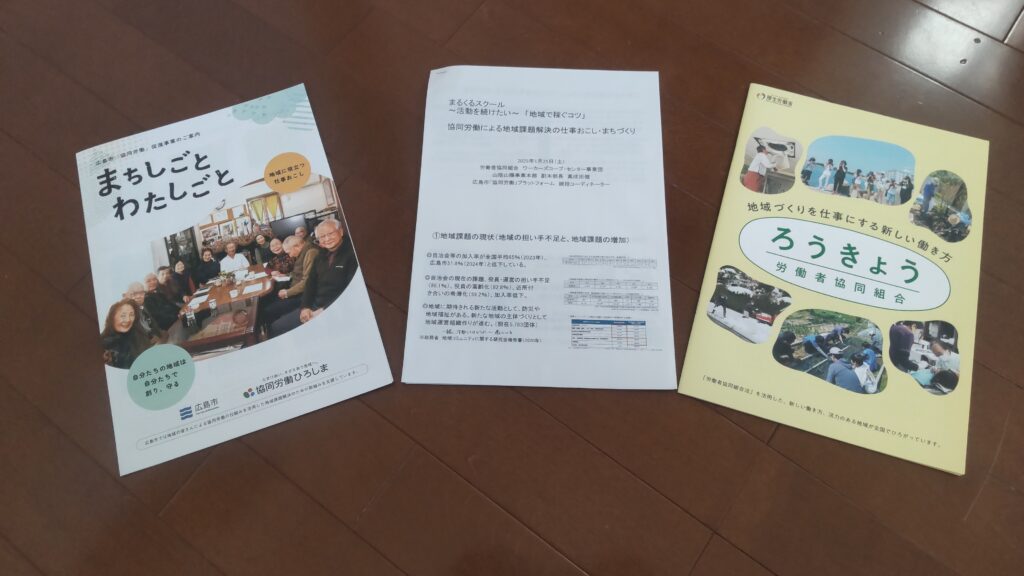令和7年1月25日(土)午前10時より大野のフジタスクエアまるくる大野で、“地域リーダー養成講座 まるくるスクール”のコース2(第2回講座)に参加してきました。
今回は「活動を続けたい!地域で稼ぐコツ」というテーマで、労働者協同組合 ワーカーズコープ・センター事業団 山陰山陽事業本部副本部長の高成田健さんにいろいろお話をいただきました。高成田さんは広島市「協同労働」プラットフォームの統括コーディネーターもされています。総勢20名弱の参加者でした。
お話は「労働者協同組合」という組織の紹介でした。「労働者協同組合」と聞くと労働組合を真っ先に思い浮かぶのですが、全く別のものだそうです。ただ、互助組織という点では筆者は似ているとも思います。
「労働者協同組合」とは、働く人たちが出資をして組合員となり、話し合いに基づいて経営や運営を行い、自ら働く協同組合なのだそうです。我々になじみのある、「生協」(生活協同組合)や農協(農業協同組合)、漁協(漁業協同組合)と同じで生協は消費者、農協は農家、漁協は漁師というように同じ立場の人々が互助を目的として結成される組織で、「労働者」という同じ立場で結成される組織を「労働者協同組合」といいます。
労働者協同組合はその組織形態などから地域の問題解決を事業化する方法として注目されているようです。具体的には組合員として出資し、自ら事業経営に参加し、自ら仕事をするというものです。会社のような労使に分かれることなく、株主利益を追求する営利を目的とするものでもない組織であるため、地域問題の解決のため、柔軟性を備えた組織体となるようです。
この日は協同組合の説明と実際の事例を高成田さんに紹介してもらいました。全部の事例の説明はありませんでしたが、いくつか印象に残った事例を挙げますと、
①長野県上田市 上田(シニア世代による地域課題解決・セカンドキャリアづくりの例)
定年退職した男性たちが、自分の特技を活かした仕事を自らつくり、地域貢献を行うというものです。屋根の塗装・営繕やエアコン修理、草刈り、穀物栽培・販売などを行い地域包括支援センターとも連携をしています。
②沖縄県宮古島市 かりまた共働組合(自治会による活用の例)
自治会役員たちによる事業化の例。幼稚園の食事づくり、もずくの加工・販売、草刈りなど地域の困りごとにスムーズに対応しています。修学旅行の受け入れなども始めるとのことです。
③島根県雲南市 うんなん(自治体による活用の例)
行政が推進する小規模多機能自治組織。20以上の事業を担うなかで労働者協同組合を設立し、雪かき、野菜収穫・缶詰加工・出荷や移送支援、温泉施設指定管理などを行っています。
お話を聞いたところ、うまく事業として軌道に乗ったものもあれば、まだまだ行政の補助金に頼る組合も多いようですべてが上手くいくことはないようです。しかし中には大成功した組合もあり十分組合員への成果分配が行われているところもあるようです。
大野第一区も自治会として様々な事業を行っていますが、同じ目的を持った人が集まり協同組合を立ち上げて組合として事業にあたるとうまくいくかもしれません。自治会が行うとどうしても「片手間」のイメージが付きまとうのですが、労働者協同組合の場合は立派なビジネスとしての活動となりますので、参加する方の意気込みも変わってくると思います。区としても労働者協同組合について情報収集・研究して利用できないか検討して参りたいと思います。
関係資料は大野東市民センター地域活動室に置きますので、興味のある方はぜひご覧ください。